トロイメライの曲の最後の方に、左手でドのオクターブ+オクターブの中のシ♭を弾く、というところがあります。これがまた、ワタシの硬い手にはきつい…。やってみてください。手をグイッと広げた状態(オクターブを弾くという状態)にすると、人差し指は親指から約90度の角度にあります。シはドの隣にありますので人差し指をグググっと親指の方へ近づけなければ弾けません。グググっと…。近づくかーい!と一人突っ込みを入れながらどうすれば弾けるか試行錯誤します。オクターブをギリギリ鍵盤の端っこ(短い方の辺の上)でとるとなんとか人差し指がシ♭に届くのですが、なんとかです。なんとか、ということは別の音に触って変な音を出す確率が高まるということでして…。うぅ…。シューマン様、ここもアルペジオにしていいですか…。
シューマン様に聞けるわけもないのでAIのCopilotに尋ねたら、『ド-シ♭-ドに手が届かない場合、アルペジオに変形するのは一般的に許容されます。特に、ペダルを使って音をつなげることで、和音の響きを損なわずに演奏することができます』と言われました。おぉ、ダメだと言われるかと…。ついでにアルペジオにするのと上のドを抜かすのとどっちが良いと思う?と聞いたら下記の答えが返ってきました。
『どちらの方法を選ぶかは、音楽的な流れや響きをどのように保ちたいかによります。
アルペジオにする場合:
- 和音のすべての音を鳴らすことができるため、作曲者の意図に近い響きを保つことができます。
- ペダルを使うことで、音のつながりを滑らかにし、豊かな響きを維持できます。
- ただし、アルペジオにすることで、和音の一体感が少し失われる可能性があります。
音を1個抜かす場合(上のドを抜く):
- 和音の一体感を保ちながら、演奏がシンプルになります。
- 上のドを抜くことで、左手の負担が軽減され、演奏が安定しやすくなります。
- ただし、抜いた音が重要な役割を果たしている場合、音楽的なバランスが変わる可能性があります。
「トロイメライ」のような曲では、響きの美しさが非常に重要です。もしアルペジオが自然に感じられるなら、それを選ぶのが良いでしょう。一方で、音を抜くことで演奏がより安定し、音楽的に説得力があるなら、それも適切な選択です。』
この『ただし、抜いた音が重要な役割を果たしている場合、音楽的なバランスが変わる可能性があります』というところにビクッとします。重要な役割をはたしているかどうかワタシにはわからないので…。右がミソなので左の上のドを外すと締まらない気はします…。ドミソが安定した和音ですよね…。やっぱりアルペジオに変更、ということで…。

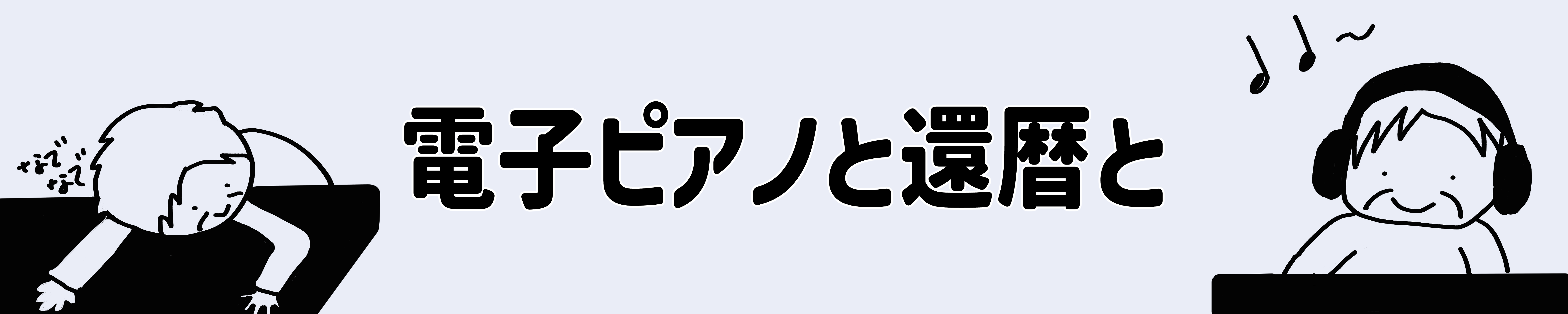



コメント